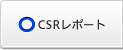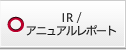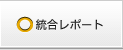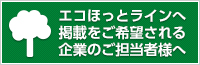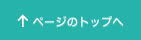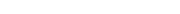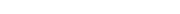メルマガ コラムバックナンバー(221号~216号)
ここでは毎月2回発行しているエコほっとラインのメールマガジン「エコほっとラインかわら版」で人気コンテンツのコラムを掲載しています。現在の主なテーマは海外企業のレポートの解説です。興味のある方はぜひ、会員登録の際に「メルマガ希望」をチェックしてご登録ください。
メルマガ会員のみの登録も出来ますので、こちらもご活用ください。
(221号/220号/219号/218号/217号/216号/バックナンバー一覧へ戻る)
小売業のサステナビリティをリードするウォルマート(後編)
前回に引き続き、ウォルマートの事例をご紹介していきます。今回のポイントは、ウォルマートに対して社会の人々が抱いている疑問、懸念に関する「情報の透明性」について。トップメッセージでは、透明性についての姿勢を次のように語っています。
「私たちは、数百、数千の地域グループやNPO、大学、企業が私たちのパートナーとなっていることをうれしく思います。このような関係を築くことで、当社の活動が持続的で定量的なものとなります。そしてウォルマートは透明性をもち誠実であることを約束しています。私たちの取り組みがうまく行った時にもいかなかった時にも。まだ当社に対して不信感のある人がいるかもしれないことはわかっています。このレポートでその不安を取り除くための努力をしています。私は皆様の考えている3つの課題に時間をとりたいと思います」
と述べて、読者の懸念に対するウォルマートの考えを以下のように示しています。
「1つめは、従業員に関して。私たちは提供する仕事や機会に誇りをもっています。離職率は業界平均よりも低く、従業員満足度は業界平均よりも高いです。30万人以上の従業員が10年以上働いています。ウォルマートでは品出しやレジ係から、部門マネジャー、店長、そしてその先まで昇格でき、これは近年の経済状況では珍しいことです」
「2つ目は、昨年秋のバングラデシュの衣服工場での悲劇です。意味もなく生命が失われたことを悲しく思い困惑しています。問題解決のために新たな支援をしました。過去数年間、より責任あるサプライチェーンを構築するために研修や監査に取り組んできました。そして私たちはゼロ容認の方針を決めました。無認可の下請けを行っているサプライヤーとは関係を断つことになります。これは、私たちにとってもその他の人々にとってもタフで重要なチャレンジです」
「最後の分野は、海外汚職行為防止法の遵守について。私たちは世界中で汚職防止のプログラムを持ち、法令違反に対して適切な対応を取っています」
問題を隠さず、正面から回答する姿勢が、信頼性の向上に必要なことを認識させてくれるメッセージではないでしょうか。
ウォルマート「グローバルレスポンシビリティレポート2013」(英文のみ) http://corporate.walmart.com/microsites/global-responsibility-report-2013/
221号(13年10月9日発行)
小売業のサステナビリティをリードするウォルマート(前編)
今回は、世界最大のスーパーマーケットチェーンであるアメリカのウォルマート社をご紹介します。
低価格を戦略とする同社は以前、非正規雇用社員の雇用条件の悪さや、出店する地域社会への配慮のなさなどから多くの批判を受けていました。しかし、経営方針を大幅に転換し、サステナビリティに配慮した企業を目指して舵をきりました。今では、サステナビリティに向けて小売業界をリードすると宣言し、先進的な取り組みを進めています。
トップメッセージは4ページにおよぶ長編で、具体的な成果がいくつも記載されているのですが、中でもポイントとなるのは商品のサステナビリティインデックスについての成果です。これは、それぞれの商品の社会環境影響を顧客にもわかるように指標化する取り組みで、以下のように述べられています。
「今年はサステナビリティインデックスによって、私たちが小売業としての本業にサステナビリティを位置づけることができるようになりました。このインデックスは、来年には400以上の商品をカバーし、プライベートブランドの設計にも影響を与えることになるでしょう」
そしてサプライヤーの影響については、
「指標を計測するためにシステマティックなアプローチを取ってきたことにより、アメリカの卸業社は年次目標の一部としてこの活動を取り入れるようになりました」
と業界全体への影響を示唆しています。サステナビリティインデックスの活動を業界全体で進めることで、顧客がより良い選択をし、社会のサステナビリティを実現したいという思いが込められています。
「私たちは業界におけるリーダーシップを強化しつづけます。ウォルマートだけでできることも重要ですが、ともに推進すればさらに効果が出るでしょう。例えば、食品に含まれる塩、砂糖、油を減らすという目標は、私たちのサプライヤーだけでなく食品業界全体にも変化を促しています。また、グリーン電力への取り組みも、業界全体にインパクトを与えています」
次回「ウォルマート(後編)」では、情報公開の透明性についてご紹介したいと思います。
ウォルマート「グローバルレスポンシビリティレポート2013」(英文のみ) http://corporate.walmart.com/microsites/global-responsibility-report-2013/
220号(13年9月25日発行)
サステナビリティへの思いを語る、ウェアハウザー
今回はアメリカ最大規模の林業会社、ウェアハウザーをご紹介します。サステナビリティと競争力を両立する「エコ+イノベーションプロジェクト」に8,200万ドルを投じて、再生可能エネルギーへの転換や水資源の保全に取り組んでいます。
新しく就任したばかりの社長のメッセージは、次のように始まります。
「私がこの会社に来て最初にしたことは、数週間にわたり現場を訪問したことです。工場に行き従業員と会い、良い所は何か、どのような改善が必要かを聞きました。現場を回って社員と対話すると、社員が労働安全に対する約束や環境への責任、地域への還元について話していることに感銘を受けました」
「従業員は優れた才能があり、歴史に誇りをもって、今の仕事に深くコミットしています。私のように、彼らもまたこの会社をよりよくしたいと思っているのです。本当に優れた会社というのは、利益をあげ、働きがいのある職場を提供し、社会に対して大きな貢献をする会社です。そこに至るために、私たちは強くなり、ギャップのあるところを改善しなければなりません」
現場を回った体験を通じて、社員自身がサステナビリティへの高い意識を持っていることを示していますが、その一方で、現状ではまだサステナブルとは言えないと語っています。
「サステナビリティは私たちの事業の進め方そのものです。しかし、私たちがサステナブルであるとはまだ言えないことはわかっています。正しい目標を設定し、その進捗を透明性をもって報告することによって、これを証明しなければなりません」
そして、取り組みの成果について具体的に示した後、次のようにメッセージを締めくくっています。
「私たちは、これらの成果を誇りに思います。しかし私たちの旅はまだ終わっていませんし、終わることはありません。世界は常に変化し、サステナビリティのための財務や社会、環境の基準はどんどん上がっています。私の目標は、ウェアハウザーが今も将来にわたってもステークホルダーの期待を超えることです」
サステナビリティへの強い思いと実際の成果について、わかりやすい言葉で簡潔に語っています。何もかも言おうとせず、非常にシンプルにまとめているからこそ、読者の心にもすんなり入ってくるのではないかと感じます。
ウェアハウザーサステナビリティ(英語のみ) http://www.weyerhaeuser.com/Sustainability/OurStory
219号(13年9月11日発行)
世界の石油会社、ロイヤル・ダッチ・シェル
今回は、世界第2位の石油エネルギー企業、ロイヤル・ダッチ・シェルをご紹介します。大きな環境課題であるエネルギーを本業にする同社は、他社に先駆けてサステナビリティへの取り組みに注力してきました。レポートの要約版が、日本語を含む9カ国語に翻訳されているというのも世界規模の企業ならではですね。
メッセージの冒頭では、世界のエネルギー環境についての認識を述べています。
「世界のエネルギー需要は伸び続けており、より過酷な環境下にある、または生産が困難なエネルギー資源の開発が求められています。当社は、いかなる場所で操業するときも、当社の従業員やコントラクター、そして近隣住民を含むすべての人々の安全を確保するため絶えず努力を続けています」
「都市部への人口集中が進み、世界人口が増え、生活水準が高まることに伴う将来のエネルギー需要を満たすためには、あらゆる種類のエネルギーを動員する必要があります。風力や太陽光などの再生可能エネルギーは今後も成長が続く一方、2050年時点においてもなお、エネルギー需要の約3分の2は化石燃料が賄うものと予想されます」
このように、自然エネルギーの活用が進んでいったとしても、まだ多くを化石燃料に依存する社会が続くことを示唆し、二酸化炭素の回収技術やエネルギー効率向上に取り組むと語っています。
そして、締めくくりには、サステナビリティに関わる重要なテーマに言及しています。
「エネルギー、水、食料という相互に関連し合う必需品に対する需要増加が世界にもたらす緊張の高まりについても、より正確な理解が形成されるよう取り組んでいます。こうした緊張は気候変動によってさらに高まると予想されます。当社は 2013年初頭に発表した新たな将来シナリオでは、急激な都市化とそれに伴うエネルギー、水、食料資源の逼迫を特徴とした、不安定な変動期における課題が焦点になっています」具体的な活動への言及がなく、今年のレポートでなくても通用しそうなところが少し残念ですが、現状と方針がコンパクトに伝わるメッセージとなっています。
Shell Sustainability Summary 2012(日本語版PDF) http://reports.shell.com/sustainability-report/2012/servicepages/previous/files/12_review_japanese.pdf
218号(13年8月28日発行)
マークス&スペンサーの進化する「プランA」
今回はイギリスの小売業、マークス&スペンサー(M&S)のトップメッセージをご紹介します。サステナビリティに向けた施策として「プランA」を掲げ180に及ぶ目標を設定しています。
冒頭では、プランAの成果とそれによる社会からの評価を強調しています。
「私はプランAの過去6年間の成果に誇りを持っています。私たちは180の約束のうち139を遂行し、150以上のサステナビリティ賞を受賞しました。賞を得るのは喜ばしいことですが、私たちは常にそれを社会・環境責任のためのビジネスを推進することや、新しい連携をつくること、そして他から学ぶための良い機会としています」
順調に成果をあげてきたプランAですが、今後の展開について次のように語っています。
「プランAの次の段階は、将来のM&Sに備えるものでなければなりません。将来の世界は、多くの裕福な顧客が新興国に住んでおり、そこでは物やエネルギー、水の供給が制限されている一方で、これまでにない需要増が起きています。プランAは、気候変動や人口の変化にも対応しなければなりません。高齢化や、若い人々の失業、栄養不足や栄養過多などの世界各地のさまざまなニーズに応えなければなりません。また、新しいメディアが生まれたことによって顧客やステークホルダーと対話する機会を得ることができ、私たちはより密接に市民の目にさらされることになるでしょう。」
そして、プランAを改善していくための動きも始まっているようです。
「この数ヶ月間、私は同僚に対して、どうしたらよりよいプランAを構築することができるか考えてもらうようにしました。国際化する小売業の課題に直面した際にも適応できるようなよりよいプランAを。ジョナサン・ポリットと社外のサステナビリティボードの支援を受けて、私たちは将来のM&Sに経済的な価値をもたらすための新しい社会環境モデルを利用した大胆な目標を策定しています」
プランAの開始から5年がたったことで、成果を評価し、今後の展開を語ることが求められる時期になりました。成果に甘んじず、さらに高い目標に向けて進んで行く様子が伝わるメッセージとなっています。
マークス&スペンサープランAレポート(英語のみ) http://planareport.marksandspencer.com
217号(13年8月15日発行)
GEの自信あふれるトップメッセージ
今回は世界中で、電気機器をはじめインフラ、素材、金融等幅広い分野でビジネスを行うアメリカの企業、ゼネラル・エレクトリック(GE)をご紹介します。
エネルギー効率の高い製品の提供と自社の成長を両立する「エコマジネーション」のイニシアチブはよく知られていますね。トップメッセージでも、エコマジネーションの効果を強調しています。
「エコマジネーションは、効率を高めることがお客様を助け、産業を変化させ、環境を守るという考えに基づいています。この良い例は、アメリカ最大の天然ガスの生産者であるクリーンエネルギーフエル社と行っている事業です。LNGを使うことで、トラックの燃料コストをディーゼルよりも25%も削減することができ、かつ排出ガスは少ないのです。しかし、このためにはインフラが必要です。私たちは主要な高速道路のガソリンスタンドにおいて、LNGを生産する新しい機器の提供を行っています。」
GEが、より良い社会のために貢献していくことを力強く語っている言葉が印象的です。
「私たちは、お客様や地域の問題を解決することと、地球やそこに住む人々および経済に利益を生む解決策を見つけることを約束しました。この約束は、私たちの経営戦略のひとつであるだけではなく、私たちの文化でもあります。責任ある事業を行うことや、GE基金の社会貢献活動、世界中で社員が行う数多くの地域貢献など、GEが社会に役立っていることに誇りを持っています。」
「私たちは、問題を解決することを楽しんでいますし、よいビジネスになると知っています。難しい課題や問題の解決のために働くことに誇りを持っています。このことは、私たちの製品そのものや、どのようにしてその製品が作られたか、そして人々にどのような影響があったかということを見ればわかります。」
自信満々のコメントです。日本のCSRレポートでは謙虚な表現が多いですが、海外の読者に届けるには、このくらい力強く発信したほうが良いかもしれませんね。
GE Sustainable Growth 2012 (英語のみ) http://www.gecitizenship.com/reports/
216号(13年7月24日発行)